(A)生計維持関係を判断するときの年収とは
生計維持関係を判断するときの年収には、給与所得、事業所得、老齢年金などの公的年金、失業給付金など名称を間わず、所得税の課税対象になっていない収入も含め、すべての収入が含まれます。すなわち所得金額ではなく全収入金額で判断されます。
したがって、自営業者の収入額は、確定申告書(税法上)の「所得金額」のみで判断せず、原則的に「売上額」から「仕入額」を差し引いた額と考えます。確定申告の「所得金額」は必要経費等の税法上の控除がされており、例えば「修繕費」、「減価償却費」等は将来の売上向上を目指すための先行投資/設備投資的な性格を有するものであり、あくまで一時的な支出と捉え「収入額」から控除しないで考えます。
社内手続き
健保組合への手続きとともに、各社への手続きも必要となります。
(B)優先扶養義務者について
民法877条は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。」と定めています。すなわち、親族は、お互いに扶養する義務があり、例えば、親に対する扶養義務は被保険者およびその兄弟姉妹にも同等の義務があるとされています。その他、以下のような事例が挙げられます。
| ・「既婚者」の優先扶養義務者 | → 配偶者 |
| ・「未婚の子」の優先扶養義務者 | → 親(父母) |
| ・「未婚の兄弟姉妹」の優先扶養義務者 | → 親(父母) |
したがって、扶養認定に当たっては、被保険者以外の扶養義務者(被保険者の両親・兄弟姉妹等)の有無とその方の経済的扶養能力等についても確認する必要があります。
社内手続き
健保組合への手続きとともに、各社への手続きも必要となります。
(C)仕送り額について
対象者が別居の場合は、対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円)未満で、かつその額が被保険者からの援助(仕送り)額よりも少ないことが必要です。
また、仕送り額は、社会通念上、大人1人が生活可能と判断される額を目安としており、当健保組合では、「最低送金目安額(1人当たりの年額)」を設定しています。この額を上回る仕送り額であるかの確認を行うことになります。
対象者の年収と仕送り額による認定関係
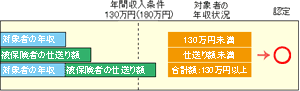
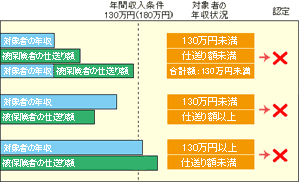
※認定を受ける時点の収入を年間に換算します。年金や失業等給付も対象となります。
(D)対象者に配偶者がいて認められない場合は?
対象者とその配偶者の年間収入額を合計した結果、「あなたからの生計費支援がなくても生計維持は可能」と健保組合が判断した場合は、「被扶養者資格が認められない」ことがあります。
当健保組合では、その判断基準となる1人当たりの生活費「基本世帯生活費」を設定しており、以下の算式により確認を行います。対象者とその配偶者の年間収入額の合計額が「基本世帯生活費」の二人分を上回る場合は、被扶養者資格が認められないことになります。ただし、適用にあたっては実情を配慮のうえ、慎重に判断することを基本としています。